第5週は通常の教室レッスンはお休み‥ということで、コンクール間近の高・大・院生4人でホールに出向きました。
リスト:メフィストワルツ。タネーエフ:プレリュードとフーガ。シューマンピアノソナタ3番。モーツァルト:幻想曲。プロコフィエフ:戦争ソナタ6番。皆大変な曲を抱えていますが、それぞれの大切な本番に向けて真摯にレッスンを受けてくれました。
以前読んだ中村紘子著 『チャイコフスキー・コンクール ピアニストが聴く現代』という本の中に、次のような一節があります。
「日本において一般的にレガートとされているタッチが、実はレガートではないということに気づいたのです。私の個人的な意見ですが、多くの日本人の演奏は、ある一定の範囲においてはレガートになっていて音楽的表現が実現できていると思います。それは、比較的ゆっくりの速度で、音量も小さいときです。これが、速いパッセージや強い和音になると、音の響きは破綻し、小ホールならまだしも、中規模のホールとなると、既にその表現は失われ、聴いている者の耳には届いてこないように感じます」
ヨーロッパに渡った子たちが一様に言うのは、正に”レガート”のテクニックのこと。求められるレガートのクオリティー”が今まて学んできたものとはまるで次元が違っていた‥というのです。そして、楽譜のレガートを実現するためには、一体どのように楽譜を読んだらよいのか、テクニックと結びつけて楽譜の中の事を学ばない限り、求められる表現には行きつかない事がわかった…というのです。
私自身を振り返っても、学生時代に学んだアナリーゼは、今思えば単に楽譜上の形式に過ぎなかったように思います。当時の自分がただただ未熟だった為ということもありますが、それは時折、生徒さん達のレッスンの中でも感じます。楽曲分析がしっかりなされていて調性感や和音がスラスラ言えたとしても、それを知ってるから、何?‥‥というような、アナリーゼが演奏に反映しない程度に留まってしまっているのです。その壁を越えるには、知識を紐解きそれをテクニックに結びつけるまでの根気、思慮深さ、忍耐力、経験……。やはり全ては、そこまで知りたい!何が何でも表現してみたい!という情熱がないと、知識の枠を超えることはできないように思います。
今マスターコースで私達と共に学んでくれている子達は、皆、本当に勉強熱心です。進学先の先生方の元で、また普通科の子達はその折々お願いするピアニスト先生方の元で、皆一生懸命模索してくれています。私や百合子先生ができることはせいぜいそのサポートで、皆が悩んでいるテクニックや先生方から頂く高度な課題を、一緒に紐解き噛み砕いてあげることくらいしかできませんが、それでも悩みの根源を突き詰めると結局すべては体に繋がるのです。諸々の事を体と結びつけてあげなかったらほぼ全てのことは実現できないと言っても過言ではありません。これは元々私達自身の悩みからスタートした事で、そこを長年模索し続けてきた結果、些細な言葉掛けが皆を広い世界へと導いたり、良い結果を生み出す事も沢山あり、お陰で10年前からは信じられないくらい深い学びをする事ができています。こうして、皆と一緒に大好きな音楽の深いところまでを勉強できることは、私たちにとっても何より幸せな時間なのです。
音楽科へ進学される方は勿論、進学しなくとも高・大生になってまでもコンクールに挑戦したいという子達は、みんな「もっとピアノが上手くなりたい…」「絶対上手くなりたい…」と思っています。欲も、根気も、センスも、全ては”好き!”から始まっているのです。
いつも音楽がすぐそばにある人生、生涯をかけて音楽をトコトン学ぶ人生は本当に豊かで味わい深いです。また、トコトンまではいかなくとも、部活や勉強や忙しい時間をぬってまでピアノを続けてくれる子達は皆本当にピアノが好きで、自らの手から音楽が紡ぎ出される時間を心から楽しんでくれています。小さなお子さん達にとって”将来ピアノが唯一無二の存在になるまで”…と考えると、気が遠くなるかもしれませんが、皆、ある意味とにかくただ淡々と日課にしてきただけのようにも思います。ですが、と同時に、幼い頃からコツコツと”好き!”を育ててあげることが本当に大切だと思います♪。時々そっぽむかれても^^;、眠くて機嫌が悪くても(^-^;めげずに頑張ろうと思います!!o(^_-)O

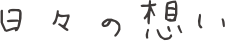



コメント