たまにSNSなどで、コンクールやレッスンに向けて親御さんがかなり細かな練習サポートをなさってる姿をお見かけますが、親御さんに本当にサポートしていただきたいことは、横についてお子さんの演奏を大人の脳や耳で作り上げてしまうことではなく、近い将来、素敵な音楽に仕上げる為の工夫やその過程をワクワクした心で取り組める資質そのものを育んでいただくことです。それも、お膳立ての末に出来上がったワクワクでなく、本当に「自ら求め自ら作り上げたワクワク」。何より自分の頭を捻って生み出した自立の音楽です。ただし、ピアノ練習は年齢以上のことが求められるので子供の脳や耳では難しい事も確かです。練習ペースも定まっていないような小さなうちは隣について励ましサポートしていただきたいですが、小学校に上がりしっかり文字も読めて、日常の練習のペースも定まってきた頃には、出来るだけ自立できるよう促してあげるのも大切な役割だと思います。発表会やコンクールが近くてどうしても気になる方は、せめて確認作業は週一回に留めて、決して上から目線でなく、手を出しすぎず、そこまで1人で頑張った事を誉めて笑顔の姿勢を貫いてくださり、あとは勇気を持ってお子さんに任せてみてはいかがでしょうか。毎日毎日親御さんがすぐ隣について、いちいち「あと一回、あと一回」と盛り上げてあげないと練習できないようでは、本当の意味で芸術ピアノには到底行き着けないように思います。そのくらいの心構えでは甘いという意味でなく、そのようなバイタリティは本人自身が生み出し育てていくモノ。横について励ましていたら、それがいくら素晴らしいサポート内容だったとしても、子供達の本来の計り知れない自立のエネルギーを奪ってしまっている事に気づいていただきたいです。
「芸術を感じる心」は、気づくこと、考えることから始まります。考えない子からは、良い感性や、芸術の心そのものは育ちにくいです。感性や芸術の心は、ただ先生の真似をしたり、親御さんに教えられて形づけられたりして手に入れられるほど単純なモノではありません。もしそうする事で演奏が良くなっているとお思いならば、いえいえ子供達の秘めたる力はそんなモノではないのです。凸凹に自ら気づき、気づいたらそれを直すにはどんな方法があるのか先生の体や手をよく見て考え(単に表面的に真似するのでなく)、そして行動に移す…。長い年月かけて、自ら気づいて→自ら考えて→自らの欲求にかられて行動に移す…その繰り返しから、ピアノのための本物の良い耳やピアノのための本物の体が生まれるのです。
どうかどうか親御さんは、賞や成績のために…または次回レッスンで先生に誉めてもらうためにお子さんの脳や耳にならないでいただきたいです。子供は、日常見聞きしているものをそっくりそのまま吸収し、それを自らの感性として貯金をしていきます。決して親御さんの物差しの中に閉じ込めてしまわず、親御さんの物差しの枠など楽々越えていけるような導きをしていただきたいと思います。子供は必ず巣立たなくてはなりませんし、親を越えなければなりません。1人でも多くのお子さんが、親御さんの価値観や感性に縛られる事なく、もっと自由に、自立した学びを手に入れてくれることを願っています。
写真は、レッスン終わりに持ち物を鞄にしまいかけて、「あっちょっと待って……蛍光ペン貸してください!」というのでペンを手渡したら、ピアノ椅子の上にサッとノートを広げて、家に帰っても練習のやり方がわからなくならないように、私が書いた練習項目に更に自分なりに絵や線を書き添えているところ。その子その子あくまで自分のペースでお家練習に向き合ってくれる姿勢は本当に頼もしいです。

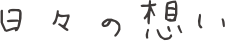



コメント