3/22大阪のいずみホールで開催される「あおによし音楽コンクール奈良」の報奨コンサートに、高校生部門で最高位を頂いた生徒さんが出演させていただきます。マスターコースの方々は日々様々な挑戦をされていますが、どの方も皆さんの取り組みは本当に素晴らしいです。作品に興味を持ち、深め、そして心から演奏を楽しんでいる姿はとても眩しく、私も学ばさせていただく事ばかりです。
ピアノコンクールは素晴らしい企画だと思います。主催する側も、そして審査する先生方も、「コンクールを通してクラッシック音楽の楽しさ・素晴らしさをしって欲しい!」と願っています。ですがピアノコンクールは、取り組み方を間違えると、子供達の好奇心の芽を摘んでしまったり、親御さんの心を苦しめることにもなりかねない事を知って頂きたいです。
実際にコンクールに向けて準備する過程は、”どのくらい芸術に近づけるか”ということから見たら発表会の比ではありません。作品に出会って、作品に興味を持って、毎日作品に向き合っているうちに好きになって、大好きになって、弾くたびにワクワクして……。ですが近年では、コンクールに挑戦される方がどんどん低年齢化して、作品への”愛情”をどう育んでいくか…など経験した事もないうちからコンクールに出場なさっている方が多いようにお見受けします。そうなると、お子さん達はコンクールにチャレンジする事をどのように捉えるでしょうか…。一つのことに向かって努力することは素晴らしい事ですし、諦めずやり続けることは心を強くします。悔しい気持ちも最大の伸びるチャンスです。が、この種の頑張り方は、「クラッシック音楽の楽しさ・素晴らしさを知る」という、ピアノコンクール本来の目的から少し横道にそれていってしまうのではないでしょうか。そして、取り組みそのものが芸術からそれて行けば行くほど、苦しくなっていってしまうように思います。コンクールは色々な意味で多くの大人が関わりますから、どうしても大人のエネルギーが強くなりがちで、もしかすると子ども達の心が置いてきぼりにされているかもしれません。お子さんがお母さんの顔色を伺ったり、先生の顔色を伺ったり、その他にも子供達の頑張りとは関係ない部分で何かしら心に引っ掛かる事があるのだとしたら、何が心に引っ掛かっているのか、是非勇気を持って立ち止まってみていただきたいです。
根気、根性、忍耐……それらとは全く次元の違う”心のひだに入り込むような感情”に出会う事ができたなら、賞など関係なく「音楽と向き合っている正にこの時間が本当に豊かで意味がある」と心から思えるはずです。コンクールに挑戦なさる方達には、是非、そのような”芸術から得られるモノ”をしっかりと受け取って頂きたいです。

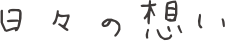



コメント